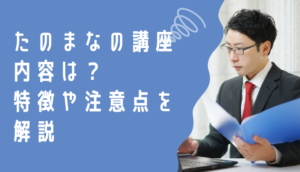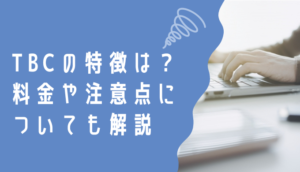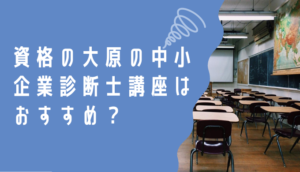今回は科目別の試験対策についてお伝え致します。「企業経営理論」科目の中身について触れているので専門用語も一部出てきますが、初学者の方でもわかりやすいように記載しておりますので、学習の指針にしていただければと思います。
一次試験「企業経営理論」試験概要
試験時間:90分
試験時間も長く、設問の文字数も非常に多い為、当科目もタイムマネジメントが重要な科目です。
先述の通り、当科目は3つの分野に大別できますが、その出題割合は概ね1:1:1となります。
出題される順番は「戦略論」→「組織論」→「マーケティング論」の順番となっていますが、その順番に解答する必要はありません。
時間が足りなくなってしまうことも想定し、自身の得意分野から解答することを推奨します。
試験終了ギリギリで得意分野に取り組みはじめたおかけで無駄な失点につながる、というようなことは無いようにしましょう。
また、学習が進んだ段階で、模擬試験等を活用し、試験本番の環境に慣れること、タイムマネジメントを練習することを心がけましょう。
配点・形式:約40問(2点×20問、3点×20問)
設問は約40問で、2点配点と3点配点の問題がそれぞれ20問程度出題されます。
設問はほとんどが選択式で、選択肢はそのほとんどが5つあり文章を読むだけでも時間がかかってしまいますので、効率的に解答する練習が必要です。
企業経営理論科目全体像
「企業経営理論」は企業を継続的に発展させる方法論を形式知化した科目です。内容は大きく「経営戦略論」「組織論」「マーケティング論」に分かれています。
中小企業診断士の勉強を進める上でも全ての考え方の基礎になる分野でもあります。
また内容も非常に面白く勉強も進めやすいため、初学者の方は当科目から学習に取り組むことが良いでしょう。
社会人の方は自身が所属・経営している会社に照らし合わせながら学習を進めていくと理解がしやすく、実務にも結びやすくなり、大いに勉強の意義を感じられると思います。
一方で馴染みやすい科目であるために、理解したつもり、覚えたつもりになりやすい科目でもあります。
楽しみながら勉強することも重要ですが、同時に「試験で正答を確保する」ことを強く意識しながら学習を進めていきましょう。
また経営理論というだけあり、範囲が非常に広く最新の理論が出題されることもあります。
そういった問題に事前対応できる受験生は非常に少ないため、特段試験対策等は必要ありません。
二次試験でも出題される重要科目
当科目は一次試験と二次試験の両方で出題されるため、一次試験の学習段階で二次試験を意識した対策を行うことが重要です。留意点等は後述しますが、そのことが良質なインプットとアウトプットにつながり、結果的に一次試験の点数上昇にもつながります。
科目合格率推移
- 2021年度:34.7%
- 2020年度:19.4%
- 2019年度:10.8%
- 2018年度:7.1%
- 2017年度:9.0%
※一次試験合格者は科目合格者としてカウントされていないため、実際に当科目で60点以上取られた方の割合は上記よりも高くなります。
近年は易化が進んでおり科目合格率は上昇傾向にあり、2021年度においては、学習が進んでいる受験生は80点以上を確保することも可能でした。
一方、2019年度までは合格率の示す通り難易度が高い科目でありました。
難易度が高い年度で重要なことは、受験生の多くが正答できる問題を確実に正答することが重要です。
その為に必要な学習の進め方、留意するべき点を記載していきます。
学習の進め方
まずは過去問を確認する
企業経営理論対策でもまずは本試験問題を確認しましょう。
他科目の解説でも掲載していますが、診断士試験では到達するべきゴールを確認した上で効率的に学習を進めることが非常に重要です。
- 90分でどれだけの選択肢を読んで、理解する必要があるか
- 学習前の段階で、経営理論への理解がどれくらいあるのか
- 戦略論、組織論、マーケティング論がどれくらいの割合でどの順番で出題されているか
などの発見や認識を学習の早い時期に得ていきましょう。この時点で過去問題を実際に解く必要はありませんが、余裕がある方は自分の専門分野の問題を解いてみるとよりイメージは掴みやすいかと思います。
専門分野であれば文章も問題なく理解ができ、知識を整理するだけで対応が可能なことも合わせて理解できるかと思います。
(例)
経営企画部で勤務:戦略論の過去問を解いてみる。
人事・組織部門で勤務:組織論の過去問を解いてみる。
企画・マーケティング部門で勤務:マーケティング論の過去問を解いてみる。
テキストに沿って学習を進める
各予備校が出版しているテキストに沿って学習を進めていくことが良いでしょう。
「経営戦略論」「組織論」「マーケティング論」の順番で掲載されているテキストがほとんどですので、まずはこの順番で読み進めていきます。
ここで注意が必要なのが「組織論」を難しく感じる受験生が多いということです。
「組織論」は3つ分野の中で、本試験での難易度も高い分野です。
ここで躓いて勉強の進捗が悪くなることやモチベーションが下がってしまうことを防ぐためにも、「組織論」よりも先に「マーケティング論」を読み進めるのも良いでしょう。
また、学習の進度に合わせて基本問題集を解くことは特にお勧めはしません。
これは本試験の問題は複数の論点が複合的に出題され、基本問題集が解けるようになっても本試験には対応できないからです。
テキストの各章ごとにある例題や過去問の改題を使用して学習を進め、テキストを一周終えた段階で早めに過去問演習に取り掛かることが効率的です。
とはいえ、各人の勉強スタイルがあり、勉強の進め方に正解はありません。
論点ごとに問題を解いてインプットする方法を得意とする受験生は、基礎問題集を使用し基礎固めをしてから過去問に取り組んでいきましょう。
過去問を1年分解いてみる
テキストを一通り終えたら本格的に過去問を解き始めますが、まずは90分の時間を測って本試験同様の環境で一度問題を解きましょう。この段階で以下のような認識を持つことが重要です。
- 90分が決して十分な時間でないこと
- テキストに載っていない内容が頻出し、テキストの知識だけでは本試験レベルの問題に苦戦すること
- 一方、知識が無くても問題文から選択肢をいくつか絞ることができること
時間内に解き切ることができない方、足切りである40点を下回ってしまう方、反対に合格点を取れる方もいると思いますが解説を見ながらどの問題で、どのように間違えたのかをしっかり分析しましょう。
過去問演習とテキストでの知識補充を繰り返す
過去問を使用して本試験で得点ができるレベルまで学習を進めていきます。
個人的には分野を絞って「演習→採点→解説とテキストでのインプット」を1サイクルとして、この小さいサイクルを繰り返していくことをお勧めします。
これは問題演習をした後すぐにその部分のインプットができることで、知識の定着がしやすくなるからです。
90分かけて演習すると、解き切った後に一科目全ての解説とインプットをすることになります。
これを全て終えるには3,4時間かかることもありますし、場合によってはインプットを不十分のまま、次の年度の過去問へ取り組む可能性もしばしばあります。
科目をまとめて演習をすることが勉強のスタイルになっている方、試験本番の環境を繰り返し経験したい方は科目ごとの演習で取り組むスタイルで問題ありません。
学習を進める上での留意点
過去問レベルのアウトプットを中心に学習を進める
学習の進め方でも触れましたが、テキストの内容理解と基本問題集でのアウトプットのみだと本試験のレベルまでの到達が難しいです。本試験を難しくしている要因は主に以下です。
- 選択肢の文章が長く、抽象的で難しい為、読解力が必要になる。
- 各分野の複合問題が出題され、テキスト内のどの知識を使用すれば良いかがわかりずらい
- 前提として試験範囲が広いため、テキストだけでは全ての知識を網羅できない。
本試験レベルの問題に対応するには、過去問を繰り返して練習するのが一番効果的です。
テキストの知識はもちろんですが、普段の業務での知識、他科目での知識、新聞・雑誌等から得られた知識、これらを広く総動員して過去問練習を行い、本試験レベルに対応できる力をつけていきましょう。
二次試験も見据えた勉強をする。
企業経営理論は二次試験でも出題され、選択肢がない状態で習得した知識を活用することが求められます。学習がある程度進んだ段階で重要論点に関しては、選択肢が無くても回答できる、知識が頭に思い浮かぶ状態を目指しましょう。
二次試験での「企業経営理論」の位置付け
- 事例I〜Ⅳ 全ての事例企業の現状を理解するための基礎になる
- 事例Iと事例Ⅱでは「企業経営理論」で学習した知識を問う、または応用して回答する問題が出題される
※事例I(経営戦略・組織論)での知識使用イメージ
「初代経営者が確立した販路を二代目経営者が引き継いできたが、売上に陰りが見えてきた。これに対して中小企業診断士として助言しなさい。」
上記のような事例と出題がされた際は
- 組織構造がどうなっているか(営業部はあるのか)
- 販路を拡大できる人材は社内にいるのか
- いる場合は評価や報酬制度は整っているか
- いない場合は教育できる体制はあるか
- それもない場合は外注するか、中途採用する必要があるが、その際の要件は何か
上記のように思考を回す必要がありますが、この時点で一次試験での知識がしっかりとインプットされているかどうかで、考えつく選択肢の数や精度に大きな差が出てきます。
具体的には
- 組織構造は機能別組織で、そのメリットは〜でデメリットは〜で、
- 人的資源管理は採用、配置、報酬、評価、能力開発の切り口で考えるとこの企業は、、、
- 中途採用のメリットは〜で、デメリットは〜で
などが頭の中ですぐに思い浮かぶレベルまで、知識の整理とアウトプットを修練していくゴールイメージを持つと良いでしょう。
マーケティング論は優先度をあげる
マーケティング論は自身の消費者経験から内容が理解しやすく、しっかり勉強することで得点限にできる分野です。内容理解と暗記で満点を狙う勉強をしていきましょう。
注意点としては、この分野はテキストの最後に掲載されていることや内容が平易であることから、勉強もほどほどに流してしまい、理解したつもりになりやすい分野です。
本試験でマーケティング論の問題で点数を落としてしまうと非常にもったいないので、テキストの内容は読み飛ばさずに丁寧に学習を進めていくことが良いでしょう。
組織論の労働関連法規は優先度を下げる。
勉強が楽しく感じる企業経営理論科目の中でも、唯一暗記をするだけの少しつまらない分野がこの労働関連法規の部分です。
本試験でも毎年2〜4問の出題があり、決して無視できない範囲ではありますが、選択肢の内容も細かい知識が記載されており難易度も非常に高くなりやすい範囲です。
社労士試験でも難問レベルの内容を問いてくる問題が出題されることもあるので、テキストで最新の情報をインプットしながら、過去問で問われやすい内容や、改訂論点を押さえる程度で問題ないでしょう。
本番は半分程度正解できたら十分と思い、あまり勉強時間をかけない方が無難だと思います。
重要論点別学習ポイント
ここからは分野ごとの重要論点に絞って、概略と学習ポイントを紹介します。
二次試験との関わり合いが強い科目であるため、一部、二次試験への対策ポイントも含めて記載しています。また、経営戦略論、組織論、マーケティング論の知識が混ざった問題も出題される為、科目の全体感は要所要所で振り返りながら学習を進めると良いでしょう。
経営戦略論
この分野は各論点が複合的に結びついた問題が多く出題されます。例えばドメインと経営戦略、環境分析と競争戦略、といったようにそれぞれの関係性を理解する必要があります。ポイントは単語の意味や各論の理解がある程度進んだのちにテキストに書かれている文章を再度見直すことです。そうすることで各論が有機的に頭の中で整理され、本試験の文章理解力がぐっと高まります。
PPMは複数事業を行なっている企業が、それぞれの事業へどの程度経営資源を振り分けるかを分析する手法です。
非常に有名な内容で、大学などの講義で既に学習済みの方も多いのではないでしょうか。
一次試験でも頻出の範囲で毎年のように出題されます。
横軸と縦軸には何の指標を置くのか、それぞれの象限の呼称は何で、その特徴はどう言うものか、PPMの問題点は何があるのか、を理解しながら覚えておくだけで点数になりますので繰り返し学習をすることで定着を図りましょう。
以下に過去問の例を記載しておきます。

※令和3年度 企業経営理論1次試験問題より抜粋
競争戦略にはポーターが提唱するものとコトラーが提唱するものに大きく分かれますが、どちらの範囲からも出題されるので、しっかりと頭の中で整理しておきましょう。
ポーターは自社が市場の中でどのポジションにいるのか、バリューチェーンの中でどこに強みがあるのかの外部・内部分析を行うことで、できるだけ競争を回避する方策を提唱しています。
具体例としては「5F(ファイブフォース)分析」によって競争環境を分析し、「バリューチェーン」のフレームワークで企業の強みを分析した上で「3つの基本戦略」から競争優位性のある戦略を策定すると言うものです。
コトラーは経営資源の質と量に応じて自社が選択する戦略を変えるべきであると提唱しています。
自社の経営資源の競争優位性を分析する手法や言葉と合わせて理解しておきましょう。
経営資源を多角的に分析するVRIO分析や、企業の中心的な強みや能力を意味するコアコンピタンス、組織として実現できる優位性を表すケイパビリティなどを自分の中で整理しておきましょう。
このような専門用語が頻出する分野は、内容を人に説明するイメージで学習を進めることが良いでしょう。
この分野は単体で出題されると正答を得やすいですが、他の内容と絡めて出題されることもあり、その場合は本試験でも難易度が高い問題が出題されています。
以下に過去問の例を掲載しておきます。

※令和3年度 企業経営理論1次試験問題より抜粋
組織論
組織論は組織構造にはどのようなものがあるか、その文化やその構成要素である人材をどのように育て、どのように管理していく必要があるのかまで広く学ぶ必要がある分野です。
その中の組織構造論に関しては二次試験でも頻出分野であるため、内容の理解をしっかりと進める必要があります。
テキストを読み進めて概略を掴んだ後は、数ある組織形態を捉えてそれぞれのメリットとデメリットを押さえていきます。
この部分は内容の抽象度が高いため、自身が属する組織の構造を思い浮かべながら学習を進めるのが良いでしょう。
人的資源管理の目的は「従業員のモチベーションを向上させることで業務の成果を高めること」です。
人材を採用して、適切な役割へ配置し、育成を通して能力開発を行い、労働の対価としての報酬を決定し、その仕事や能力を評価する、その全ての管理活動に関して学びます。
一次試験と二次試験の両方で頻出であるため、何も見なくても知識が頭に浮かぶレベルまで学習を進めましょう。
ポイントは、まずは人事制度全般の構造を理解し、それぞれの制度について実際に自身の組織ではどのようなものがあるのかを想像しながら覚えていきます。
人事制度はおおよそ4つに分類されます。
「採用」、「賃金」、「能力開発」、「評価制度」ですが、(頭文字で「さちのひ」と覚える)このうち最も大事なものは「評価制度」と言われています。
評価制度は従業員それぞれに取って満足いくものを作ることが非常に無ずかしく、また評価者の教育も同時に行わなければ運用はうまくいきません。
どの企業でも評価制度の構築、その運営には経営者と人事部が頭を悩ませています。
重ねてではありますが、人的資源管理に関わらず組織論全般は抽象的な表現が多いため、上記のように具体的な企業や自身の経験をイメージしながら勉強を進めていくことが重要です。
マーケティング論
この分野では企業が売上を上げる仕組みに関して学びます。
その中でも診断士試験では伝統的でオーソドックスな理論を主軸に学び、その各論として最新の手法も学んでいきます。
その他の理論が出題される可能性もありますが、テキストと普段の生活の知識で十分に合格点は確保できると思います。
マーケティング論に一般的な正解は存在しませんが、実務でも思考の切り口として大いに役立ちますので組織論と同じく社会の商品、サービスと照らし合わせながら学習を進めていきましょう。
営業戦略を考える際には、自社の市場でのポジショニングと、ターゲットとなる顧客のセグメント分析を行なった後、具体的な施策を考える際に使用するのがこのマーケティングミックスです。
最近は一次試験でも知識を問うだけでなく応用的な問題が出題されることもありますが、文章をしっかり理解し知識を活用すれば正答ができる問題がほとんどです。
一方、範囲が広いためテキストにも載っていない細かな知識を問われた場合は捨て問として良いでしょう。
二次試験ではこの4Pの知識をフルに活用しながら、具体的な施策を助言する必要があります。
4つのPそれぞれにはどのような施策があるのかを頭に思い浮かべられるレベルを目指しましょう。
(例)
Product:品揃えを拡大する、女性向けの商品を開発する…etc
price:クーポンで再来店を促す、◯◯を特典としたCPを催す…etc
まとめ
前述のとおりですが、企業経営理論は中小企業診断士試験の核となる科目です。
二次試験を突破する力を養うことを前提に勉強を進めることで一次試験の対策にもなります。
実際の企業と結びつけて具体的なイメージを膨らませながら勉強していきましょう。