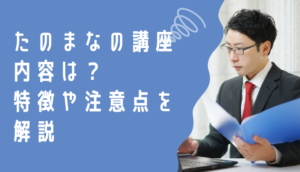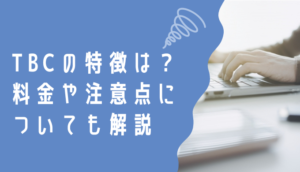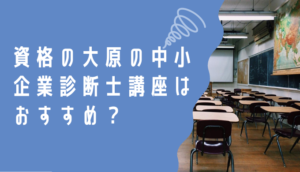今回は科目別の試験対策についてお伝え致します。
『経営法務』科目の中身について触れているので専門用語も一部出てきますが、初学者の方でもわかりやすいように記載しておりますので、学習の指針にしていただければと思います。
※法律用語等を平易な言葉で説明しているため、法律上正しくない表現が含まれている可能性があります。ご了承ください。
一次試験『経営法務』試験概要
試験時間:60分
与件文としてA4用紙1ページほどの事例が与えられていたり(中小企業診断士と会社社長の会話形式など)、選択肢の文章が長くなっていたりと、問題の設定を読み取ることと選択肢の正誤の判定を行うのに時間を要する問題が多くなっています。
この試験に慣れていないと60分の時間では全ての問題に取り掛かれないで程の文章ボリュームがあります。文章の読むスピードを上げるなど60分間で全ての問題に対応できるように準備を行う必要があります。
配点・形式:4点×25問
問題数は25問で配点は全て4点です。解答の選択肢は直近では全て4択となっています。
科目合格率推移
- 2021年度:12.9%
- 2020年度:12.0%
- 2019年度:10.1%
- 2018年度:5.1%
- 2017年度:8.4%
※一次試験合格者は科目合格者としてカウントされていないため、実際に当科目で60点以上取られた方の割合は上記よりも高くなります。
直近の科目合格率としては他科目と比べて最も低い科目です。
科目合格率が1桁になる年も多く、2018年度においてはあまりにも難易度が高すぎたため、全受験者に8点の加点(得点調整)が行われています。
多くの受験生にとっては得点源にする科目ではなく、足切りにならないような対策をとる科目といえます。
経営法務科目の全体像と学習方針
経営法務科目では、中小企業の経営者や起業者、知的財産権を取り扱う人に対して助言を行う為の法律や制度、手続きに関する知識が求められます。
手続き業務を実際に行うのは、司法書士や弁理士などの専門家ですが、中小企業診断士は中小企業経営全般のコンサルティングに携わるため、法務に関しても一定の知識を備えておく必要があります。
出題される領域は大きく以下の3つに分けることができます。
民法+その他
民法とは、私人相互間での規律について定めた法律で、総則・物件・債権・親族・相続の5つの編から成り立っています。
中小企業診断士の試験範囲として明示されているのは物権・債権・相続です。
会社法
会社法とは、会社の設立・運営・清算などのルールや手続きを定める法律です。
中小企業診断士の試験範囲では、会社の設立手続き、それぞれの会社の種類(株式会社や持分会社等)の機関の詳細、会社の組織再編や倒産手続き等について学びます。
知的財産権
知的財産権とは、著作物(著作権)や発明といった無体物に対してそれらを保有するための独占した権利を与えるものです。
中小企業診断士の試験範囲では、メインとしては産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)について学び、付属する形で著作権や不正競争防止法、独占禁止法等について学びます。
これら試験範囲に対しての出題実績としては、以下の割合です。
民法+その他:会社法:知的財産権 = 2割強:4割弱:4割弱
これらを踏まえて、試験対策として最も優先的に取り組むべき分野は知的財産権になります。
知的財産権の分野ではある程度出題される内容が限られており、また会社法の分野よりもイメージがつかみやすく暗記がしやすいためです。
単純な暗記で正答が可能な難易度の低い問題も出題されやすい分野です。
次いで学習を行うべき分野が会社法です。
こちらも出題比率が高く、出題分野もある程度限られています。
知的財産権と比較して、知識が入り組んでおり暗記が難しいために優先度を下げています。
最後に最も優先度を下げてもよいのが民法です。
出題比率が低いのもそうですが、試験範囲が広く学習が間に合わないこと、難易度の高い問題が出題されやすいことが要因です。
商品開発等の業務に携わっている人であれば知的財産権に関して多少の前知識がある方もいるかもしれませんが、会社法や民法に関しては知識がない方がほとんどだと思われます。
覚えることが多く、取り掛かりにくく、苦手とする受験生が多い科目ですが、どの受験生もスタートラインが同じです。
学習を進めることがそのまま他受験生との差をつけることに繋がりますので、根気よく学習に取り組んでいきましょう。
学習の進め方
過去問を確認する
当科目においても、まずは過去問を確認しどのような出題形式なのかを確認していきます。
特に確認していただきたいのが以下です。
- 問題文のボリュームが多く、文章を早く読み解く力が必要であること
- 単語の穴埋め問題が一定数あること
- 金額や日数といった数字を問われるシンプルな問題が一定数あること
一つ目は、事例タイプの問題は問題文に会話のやりとりが盛り込まれ、非常にボリュームがあります。(過去問で後述します。)
文章を理解するまでに時間とスキルが必要な問題が複数出題されています。
二つ目と三つ目は、用語の意味を正確に把握さえできていれば正答が可能な問題も一定数あり、数字や重要ワードを意識して勉強する必要があります。
これらの全体感を把握して、自身の学習の到達点のイメージを掴むことができれば十分でしょう。
過去問を実際に解いてみる必要はありません。
問題集を活用しつつ、テキストでのインプットを行う
続いてテキストに沿って知識のインプットを行っていきますが、その順番に関しては前述の通り、
知的財産権→会社法→民法
の順番で学習を進めることをお勧めします。
一般のテキストでは、民法→会社法→知的財産権の順番で記載されているものが多いと思いますが、上述した通り、出題比率や暗記のしやすさから学習の優先度が高い分野は知的財産権の分野です。
まずは取り掛かりやすく得点源にしやすい分野から学習することで、精神的に他分野の学習にも取り組みやすくなります。
学習の進め方としては、1セクション読み終えるごとに基本問題集に取組み、知識の確認を行いながら学習を進めていきます。
当科目のテキストを読み進めていると、覚える用語や数字が多すぎて何をどこまで覚えればよいのか分からないといった状態に陥ります。
そのためまずはテキストでのインプットは全体感を掴むように読み進め、その状態でその分野の基本問題集に取組みましょう。
基本問題集でどの知識がどのように問われているのかを確認することで暗記していくポイントを掴んでいくように進めていけば問題ありません。
当科目においては、テキストに記載されている知識を網羅的に暗記するのは至難の業です。
基本問題集や過去問演習を繰り返していくうちに持っている知識は広がっていくので、あまり気負わずにテキストでのインプットを進めていきましょう。
過去問でのアウトプット、テキストでのインプットを繰り返す
ある程度テキストでの知識補充が進んだ方は、続いて過去問に取組んでいきましょう。
当科目の問題文はボリュームがあるため、取組むには骨が折れますが、過去問演習は絶対におろそかにしてはいけません。
まずは事例タイプの文章問題に慣れるようにしましょう。
このタイプの問題に対応するには用語の知識だけではなく、文章読解力も必要になってきます。
裏を返すと、知識が不安定でも文章読解力に優れていれば正答を導ける場合もあります。
こういった文章問題に慣れていれば60分の試験時間もゆとりをもって使うことができるので、練習を繰り返しておきましょう。
それ以外の問題においては、特に受験者の正答率が高い問題(正答率60%以上)に着目して演習を行っていきましょう。
これらの問題に出てきた知識があいまいな場合は、テキストに立ち返って知識を補填する必要があります。
難易度の高い問題が多い科目ですので、基本問題は絶対に落とせません。
当科目の知識を全て暗記するのは難しく、またテキスト範囲外の知識が出題されることも多いため、正答率の低い問題の知識に関してその全てを理解・暗記する必要はありません。
このような法律や決まりもあることを知る程度で良いでしょう。
過去問演習を繰り返す中で押さえるべき知識に優先度をつけながら学習を進めていきましょう。
学習の留意点
テキスト1周目の学習にはあまり時間をかけない
当科目の内容はそれぞれの用語で類似した内容が多く、それらを網羅的に暗記することは非常に労力がかかります。
そのためテキスト1周目の学習においては、あまり時間をかけずに要旨を掴む程度に留め、先に読み進めていくようにしましょう。
問題演習を行っていく段階で、テキストを振り返りながら覚えなければいけないポイントを掴んでいくことを繰り返していくうちに知識は安定していきます。
テキスト1周目のインプットの段階で時間をかけてしまうと嫌になってしまい、学習が滞ってしまう原因になります。
各論を比較することで、総論での暗記を心掛ける
例えば知的財産権の中の産業財産権の分野では特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった4つの権利について学習するのですが、一般のテキストではそれぞれの権利について順番に学んでいきます。
特許権の審査の流れは〇〇で、要件は〇〇で、存続期間は〇〇。
実用新案権の審査の流れは〇〇で、要件は〇〇で、存続期間は〇〇。
といった具合です。
テキストを初めに1周学習する際にはこの通りに学習することは問題ないのですが、テキストでのインプットを終えただけでは、問題を解く段階で必ず各分野の知識が整理できなくなってしまいます。
そこでお勧めしたいのが以下のように部門横断で知識を整理して暗記することです。
| 特許権 | 実用新案権 | 意匠権 | 商標権 | |
| 要件 | 容易に発明 できないこと | 容易に考案 できないこと | 工業上の利用 可能性があること | 自他商品 識別能力を持つ |
| 無効審判 | 利害関係人のみ、 いつでも | 誰でも、 いつでも | 誰でも、 いつでも | 利害関係人のみ |
| 存続期間 | 出願から20年 | 出願から10年 | 出願から25年 | 登録から10年 |
問題演習後、間違った知識を確認する時には上記のような整理された表を確認することで、類似の別論点に関しても合わせて見直すことで効率的に知識を補填することができます。
こういった部門横断的に知識を把握することは、知的財産権だけではなく会社法全般の論点でも役立ちます。
英文契約書問題対策は頻出英単語の暗記のみに留める
英文契約書に関する問題(5~20行ぐらいの英語で記載された契約書が示され、それについて解答する問題)が毎年1~2問出題されます。
毎年のように出題される問題ですので得点できるに越したことはないのですが、英語力は一朝一夕で身に付くものではありません。学習の時間効率を考えてお勧めしたいのは、頻出英単語の暗記になります。
bankruptcy:倒産、confidentiality:秘密保持、tax evasion:脱税
など契約や税金に関する英単語の意味を押さえておきましょう。
問題文には関連する文章が日本語で、合わせて記載されていることがほとんどですので、ポイントとなる単語の意味さえ掴めていれば対応できることも少なくありません。
自身の英語力と相談にはなりますが、あまり時間をかける分野ではありませんので効率的に得点できるようになることを心掛けましょう。
関連他資格には基本的には手を付けない
テキストの範囲外の内容が出題されることも多く、それらもカバーしたいと考える受験生の方もおられるかもしれません。
経営法務科目に関連する他資格としてビジネス実務法務検定や知的財産管理技能士などがあげられますが、これらには手をつけないことをお勧めします。
試験範囲が重複していない分野もあり、時間効率が悪いからです。
中小企業診断士の短期合格を目指す受験生であれば、経営法務のテキスト範囲のみでの学習が効率的です。
もし、多年度受験生などでモチベーション維持に悩んでいる方であれば上記資格を受験してみるのも有りでしょう。内容的には経営法務の学習にも役に立ちます。
論点別学習ポイント
ここからは論点別の学習ポイントと過去問での出題例を紹介します。
知的財産権
知的財産権は大きく、産業財産権とそれ以外に大別することができます。
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)
産業財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を総称したもので、新しい技術やデザイン、商標などに権利を与えて、模倣防止のために保護し、信用を保持することによって産業の発展を図ることを目的として制定されています。
診断士試験においては、特許権、意匠権、商標権に関する内容が頻出分野となっています。
出題形式としては、単純に用語の意味を問うものもあれば、事例形式で出題されるものもあり様々です。
対策のポイントとしては用語の意味を正確に暗記することと、上述した通り部門横断的に知識を整理して把握することです。
それぞれの権利に共通するものがある一方で、期間や制度の一部が違うもの、それぞれの権利に特徴的なものに注意して暗記をしていきましょう。
基本的な問題が出題されやすい分野になりますので、ぜひ得点源にしたい分野となります。
過去問では以下のように出題されています。

産業財産権以外
産業財産権以外の分野では著作権と不正競争防止法が頻出の分野となります。
産業財産権の分野と同じような形で出題され、同様に用語の意味を正確に暗記することが重要となります。
過去問では以下のように出題されています。

※令和3年度 経営法務1次試験問題より抜粋
会社法
当分野ではまず一番に押さえなければいけないのが株式会社の機関設計分野です。
株式会社を設立する上で様々なルールがあります。例えば
取締役は1人以上必要、大会社の場合だと会計監査人の設置が必要、などがあります。
これらを文章で暗記するのは非常に効率が悪いため、図で体系的につかむことをお勧めします。
以下にサンプルを貼り付けています。
初学者の方がこれを見ても全くわからないとは思いますが、テキストを1周読んだ後に下図を見れば、確実に暗記の役に立ってくれます。


(引用元:https://rmc-oden.com/blog/archives/124761 【渾身】図で覚える 株式会社の機関設計 (経営法務)【中小企業診断士】)
そのほか以下リンクの書籍、

「一発合格まとめシート」では分かりやすく図にまとめてあり、暗記の助けとなります。
短時間で効率的に暗記を進めたい方にとってはお勧めの書籍となります。
それ以外にも覚えなければならない内容が多い分野ですが、テキストに載っていない内容が出題されることは少なく、きちんと暗記と理解を進めれば得点源とすることができます。
当分野が合格点獲得の分岐点といえる分野ですので、正確に知識が暗記できるまで時間をつかって学習すべき科目といえます。
過去問では以下のように出題されています。


※令和2年度 経営法務1次試験問題より抜粋
民法+その他
民法
出題比率も多くなく、難易度の高い問題が出題される割合も多いため、学習の優先度は低い分野です。
テキストに記載されていない内容が出題されることが多く、その場での対応が難しい問題が多い範囲です。
社労士試験や行政書士試験など法律に沿った試験の場合と同様に、診断士試験の民法分野でもイレギュラーなケースに関して出題されることが多く、細かな知識が問われています。
これらを診断士のテキストで網羅的に暗記するのは無理がありますし、効率が良くありません。
当分野に関しては、基本的な論点の暗記のみで学習は留めておきましょう。
当科目の本試験では、選択肢が全て4択となっており、民法に関しては一般常識で選択肢の1つぐらいは消去することができます。
ランダムに選んでも3問に1問は正解できると捉え、深入りしないようにしましょう。
過去問では以下のように出題されています。

※令和2年度 経営法務1次試験問題より抜粋
その他
上記以外の出題分野として国際取引や英文契約書、景品表示法などが出題されます。
上述した通り、英文契約書の問題はほぼ毎年出題されていますが、学習の時間効率の悪い分野になります。
あまり時間をかけずに頻出単語の意味を押さえる程度に留めておきましょう。
過去問では以下のように出題されています。

※令和元年度 経営法務1次試験問題より抜粋
まとめ
基本的には短期記憶で対応する科目ですので、比較的後半に学習する方が多い科目だと思います。
なかなか学習のモチベーションが上がりづらい科目だと思いますので、上述した通り、それぞれの論点にあまり深入りせずに短サイクルでインプットとアウトプットを回していくようにしていきましょう。
経営法務科目の内容は、多くの方にとって普段の業務や日常生活にもなじみの薄いものになります。
そのため、こういった法務の内容を押さえている中小企業診断士には価値があります。
自身が中小企業診断士となり、実際に中小企業の社長に法務のアドバイスしている姿を想像してモチベーションを維持しながら学習に取り組んでいきましょう。