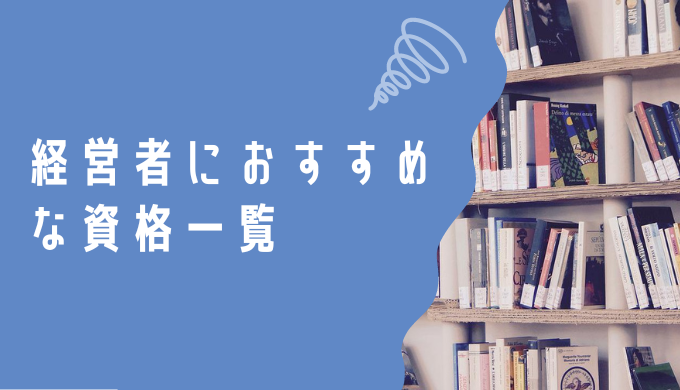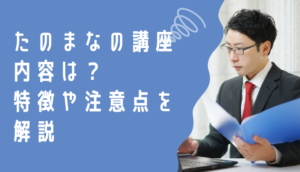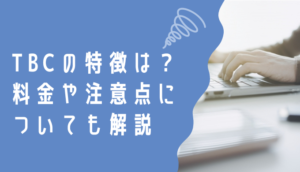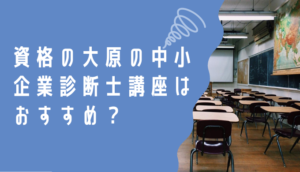これから経営者を目指す大学生、または既に会社経営している人の中には、経営に役立つ資格を取得したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
経営者におすすめな資格は多種多様で、難易度もそれぞれ異なります。
そのため、実際にどのような資格を取得すればいいのかわからない人もいらっしゃることでしょう。
そこでこの記事では、経営者や経営者を目指す人におすすめな資格一覧を紹介します。
この記事を読むことで、経営者が資格を取得するメリットや経営に役立つ資格の種類が明確にわかります。
本記事を読み、自分の目的にあった資格を取得しましょう。
経営者・経営者を目指す人が資格を取得すべき理由
会社や店舗などを経営する際、必ずしも資格は必要ありません。
しかし、資格を取得することでさまざまなメリットが得られます。
この項目では、経営者や経営者を目指す人が資格を取得すべき理由について紹介します。
知識やスキルアップにつながる
資格取得を目指し勉強することで、経営に役立つ知識やスキルアップにつながります。
時代の流れと共にデジタル化が進んでいる状況下において、経営者にはマネジメント知識だけでなく、マーケティングや情報関係などのさまざまな知識が必要です。
もちろん、知識やスキルが備わっている専門家を雇用するという選択もあります。
しかし、経営者自身が専門家を選択する上では、最低限の知識が必要になるのです。
勉強により得た知識やスキルは、ビジネスにおいてのさまざまなシーンで活用でき、役に立つでしょう。
経営に関する判断能力が向上につながる
早急な判断が求められる状況やトラブルの際に、物事を適切に判断する能力が向上します。
資格を通してさまざまな知識やスキルが身につき、経験していないことも合理的、且つ論理的に考えられるからです。
人は成功と失敗、両方の経験により学び、知識が増えて次第に適切な判断ができるようになります。
しかし、いくら長年経営してきた人でも想定できないトラブルは生じます。
その際に必要なのは、さまざまな状況に対応する判断能力です。
資格を取得すると、一定の分野に対する知識やスキルが得られることはもちろん、それを応用してさまざまな状況に対応できます。
信頼感が生まれる
資格を所持することで自分が何に対して知識やスキルがあるのかを証明でき、他人・他社に信頼してもらえます。
専門知識を学んできた努力と会得した専門知識の明確な証拠になるからです。
例えば家電製品を販売する店舗において、ただ商品に詳しいスタッフと家電製品アドバイザー資格保持者とでは、ユーザーの信頼感が異なります。
自社サービスの提案や提供する際に説得力が増し、ユーザーの需要を高められるでしょう。
経営におすすめな資格一覧
資格を取得するには明確な目的設定が必要です。
マネージメント関する資格や会計、経理に関する資格など、数多くある資格から適切な資格を選択できるからです。
ただ漠然と、経営に役立つ資格を取得しようとする人も少なくありません。
確かに、それでも資格は取得できますが、実際に会社経営する際などに役立たない可能性もあります。
大切なのは資格を通して具体的に何が得られるのかです。
経営におすすめな資格は次の通りです。
- 中小企業診断士
- マーケティング・ビジネス実務検定
- ビジネスマネジャー検定
- メンタルヘルス・マネジメント検定
- 企業経営アドバイザー
- ビジネス実務法務検定
- 経営士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 日商簿記検定
- 公認会計士
- 秘書技能検定
- MBA(経営学修士)
それぞれの資格について、内容や試験の難易度などを紹介しますので、資格を選択する際の参考にしてください。
中小企業診断士
中小企業診断士は、中小企業の経営課題を解決するために助言や提案を行う専門家です。
財務や経理だけでなく人材育成、マーケティングなど、経営に関連する幅広い知識が身につけられます。
そのため、経営者以外にも弁護士や税理士などが資格を併有している場合もあります。
企業の成長戦略策定や実行にあたってのアドバイスが具体的な業務で、経営コンサルトの国家資格です。
1次試験はマークシート形式、2次試験は記述と面接形式です。
合格率は1次試験が17%〜42%、二次試験が18%〜20%(2015年〜2021年のデータ)と、比較的に難易度が高い資格です。
[出典:https://www.j-smeca.jp/attach/test/suii_moushikomisha.pdf]
中小企業診断士として登録し活動するためには、1次試験を合格したあと2回以内の受験で2次試験に合格し、実務補修を受けるか実務に従事する必要があります。
マーケティング・ビジネス実務検定
マーケティング実務に関する知識を総合的に判定する検定です。
マーケティングの基礎知識やスキルを応用したプロモーション戦略、関連法規などを幅広く得られます。
マーケティング・ビジネス実務検定はA級・B級・C級の3段階に分かれています。
- A級:マーケティング戦略の立案や意思決定、管理、判断業務ができるレベル
- B級:マーケティング業務の運用ができるレベル
- C級:マーケティング定型業務ができるレベル
試験は年に4回実施されており、難易度は比較的に低いため取得しやすい資格です。
ビジネス実務法務検定
ビジネスのさまざまな分野における実務レベルの法的知識を学べる資格です。
取引における契約書の締結や債権回収などの財産管理、労働基準法に準じた雇用契約書の策定などの業務を行います。
試験は1級〜3級まで設けられており、学生や社会人から法務部署の所属者及び責任者まで、レベルに応じて受験できます。
企業が提供するサービスにおいて、法律上の問題やそれによるリスクを防ぐのに役立ちます。
税理士
税金の専門家として活躍できる国家資格です。
税理士の仕事は、所得税や法人税、相続税などの申告の代行や相談を受けることです。
加えて、決算書作成などの会計処理のサポート、資金調達や収益向上、M&A、事業承継などのアドバイスや支援なども行います。
税理士の資格を保有することで、節税や税理士の雇用費用の削減ができ、コストカットにつながります。
税理士の試験は、11科目中から5科目を選択して合格しなければならず、難易度も非常に高いといわれています。
ただし、選択科目を1教科ずつ受験できるため、時間をかけ集中して勉強することで合格が目指せるでしょう。
取得後、行政書士連合会に登録し行政書士としての活動も可能です。
社会保険労務士
人材に関する労務管理や社会保険の専門家であり、社会保険労務士法に基づく国家資格です。
人事や労務管理などに関する労働問題の解決や、社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与します。
医療保険や年金制度に関しての知識も身につくため、職場環境の改善にも役立つでしょう。
試験範囲が広いことから合格率は、およそ6%〜7%低い割合です。
勉強時間を確保し、長期的に資格取得を目指しましょう。
公認会計士
公認会計士は、会計監査の専門に行う国家資格です。
簿記検定やビジネス会計検定など、さまざまな会計資格の中でも最高峰といわれています。
財務諸表監査は公認会計士の独占業務です。
企業の決算書をチェックするなど会計業務に不正や間違いがないか判断します。
弁護士や医師と並ぶ三代国家資格とされており、試験の合格率は5%〜10%ほどしかない難易度の高い資格です。
試験は、年齢や学歴、職歴など関係なく誰でも受けれらます。
公認会計士の資格取得後は、税理士、行政書士に登録もできるため、経営に関しての幅広い分野で役立つでしょう。
MBA(経営学修士)
MBAとはMaster of Business Administrationの略称です。
経営学の大学院修士過程を修了すると取得できる学位で、経営の3要素である人・物・金についての知識が身につきます。
これまではアカデミックなカリキュラムが基本とされていましたが、近年ではテクノロジーや新たなデザインを取り入れて、実践的なカリキュラムを提供している大学院もあります。
資格自体が経営者の育成を目的としているため、実際に経営に携わる際には役立つでしょう。
中小企業診断士がおすすめな理由
中小企業診断士は、その汎用性の高さから幅広い分野で活用できます。
財務や経理、人材育成、マーケティングなど、会社経営に必要な知識を総合的に学べるからです。
また、業務独占資格ではない分、企業内でも活用しやすいというメリットがあります。
コンサルタントとして独立することはもちろん、コンサルティング会社で働くこともできます。
資格取得後、学んだ知識をすぐに活用できるため、最近では多くの人に注目されています。
他の資格との比較をした記事はこちらです。→http://xs676435.xsrv.jp/shikaku/513
まとめ
この記事では、経営者や経営者を目指す人が資格を取得するメリットや、経営におすすめな資格について紹介しました。
経営に関する資格を取得することで知識やスキル、判断能力など総合的な能力の向上につながります。資格取得に向けた努力と専門知識を習得したことが認められ、信頼感も増すでしょう。
経営に役立つ資格は、本記事で紹介した中小企業診断士を含む7つの種類から、目的に応じて適切に判断しましょう。