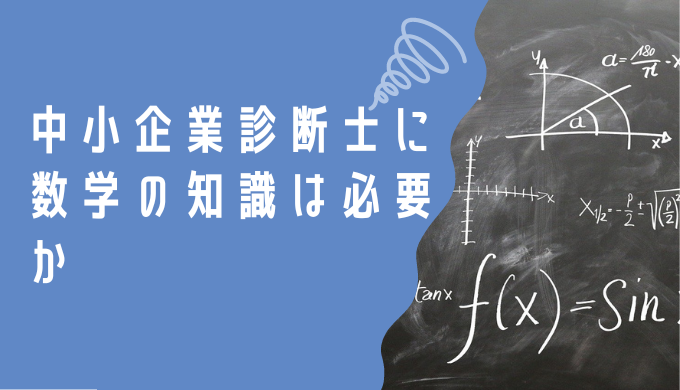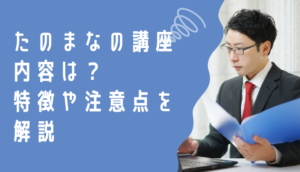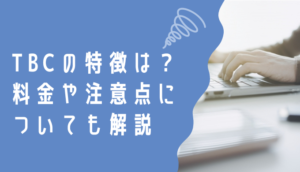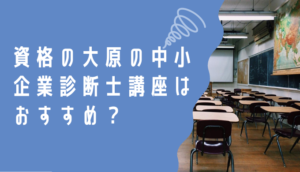中小企業診断士の試験には、経済や経営、財務・会計などに関する問題が出題されます。
企業の経営課題や成長戦略に対しアドバイスするためには、さまざま分野の知識が必要になるからです。
そのため、中小企業診断士には数学の知識が必要であるのか、また、必要であればどの程度の知識が必要になるのか疑問をお持ちの方も少なくありません。
そこでこの記事では、中小企業診断士について、数学知識の要否や必要な場合の数学知識レベルなどを、実際の問題を交えて紹介していきます。
中小企業診断士に数学の知識は必要
中小企業診断士の試験に合格するためには、数学の知識が必要です。
ただし、難しい方程式や図形、微積分に関する深い知識は必要ではありません。
出題される問題は、四則演算や表や図の読み取り、簡単な公式の理解などがあれば解答できるレベルです。
数学に対して苦手意識のある人でも対応できるでしょう。
中小企業診断士の試験制度
中小企業診断士の試験は、選択式問題の1次試験と筆記式の2次試験で構成されています。
2次試験を受験するためには1次試験の合格が必要です。
合格には、1次、2次試験共に全科目の平均が60点以上あることに加えて、40点未満の科目がないことが条件です。
2次試験合格後の口述試験(面接)ではほとんど全員が合格しています。
1次試験(選択式)は全7科目
1次試験は次の7つの科目で構成されてます。
- 経済学・経済政策
- 財務・会計
- 企業経営理論
- 運営管理
- 経営法務
- 経営情報システム
- 中小企業経営・制作
前述した通り、これらの全科目の平均が60点以上で、尚且つ40点未満の科目がなければ合格になります。
2次試験(記述式)は全4科目
2次試験は次の4つの科目で構成されています。
- 組織
- マーケティング・流通
- 生産・技術
- 財務・会計
2次試験の合格条件も1次試験と同様です。
中小企業診断士試験で数学が必要な科目の特徴
中小企業診断士の1次試験と2次試験を通じて、数学が必要な科目は主に次の5つが挙げられます。
- 経済学・経済政策
- 財務・会計
- 運営管理
- 経営法務
- 経営情報システム
これら5つの主な問題内容や傾向について紹介していきます。
経済学・経済政策
経済学・経済政策科目では、マクロ経済学やミクロ経済学についての問題が中心に出題されます。
マクロ経済学は、政府や企業、家計を一つにまとめた社会全体の動きを学ぶ学問です。
中小企業診断士の試験では、国民所得や投資、消費、備蓄などに関する内容が中心です。
一方、企業や一個人の経済活動を学ぶミクロ経済学からは、企業の生産活動や家計の消費活動に関する問題が、それぞれグラフや計算式を用いて出題されます。
指定された条件にもとづき、数値の計算や経済理論を表したグラフを読み取りする知識が必要です。
過去の問題では、貯蓄・投資図やデフレ・ギャップ、GDP・物価指数、需要と供給、IS-LM分析、労働生産性などに関して、毎年10問程度出題されています。
財務・会計
財務・会計科目は、計算や仕訳などに関する問題が毎年約10問出題されます。
財務・会計では、財務諸表等を用いて企業の状態を把握し問題点を分析します。
そのため、利益や資産、資産などの状況を理解し、分析するための知識が必要です。
具体的には、損益計算書や貸借対照表などの会計の基礎、ファイナンス理論など幅広く出題され、尚且つ計算問題の割合が高い傾向があります。
ただし、計算問題は公式に当てはめることで解答できるレベルですので、心配無用です。
運営管理
運営管理科目では、運営管理の効率化を図る計算問題が約5〜10問出題されます。
製造業や流通業、小売業などのジャンルにおいて、生産管理と店舗・販売管理との大きく2つに分類されています。
1次試験では、生産形態と生産方式の分野から、受注・見込み生産、個別・ロット・連続生産、ライン生産、セル生産などについて出題される傾向が高いため、用語や特徴を理解しておきましょう。
この科目は2次試験のマーケティング・流通、生産・技術につながる内容なため、しっかり学習しておくと良いでしょう。
経営法務
経営法務からは、相続に関する計算問題が出題されますが、過去のデータよると出題される確率は少ない傾向があります。
相続分(取得額)についてポイントを押さえておきましょう。
経営情報システム
経営情報システムも経営法務と同様、計算問題が少ない確率で出題されます。
問題は、プロジェクトの進捗率などを分析する管理手法についての内容です。
簡単な計算式で解答できるため、問題の出題形式に慣れておくことが重要です。
中小企業診断士に必要な数学の知識レベルを検証
この項目では、過去問をいくつか紹介し、実際に問題を解いてどの程度の数学知識が必要なのか検証します。
検証1.経済学・経済政策科目の過去問
問)生産物市場の均衡条件は、総需要=総供給である。総需要ADと総供給ASが以下のように表されるとき、下記の設問に答えよ。
AD = C + I + G C = C0 + (c Y – T) AS = Y
ここで、C は消費、I は投資、G は政府支出、C0 は基礎消費、c は限界消費性向 (0 1 c 1 1)、Y は所得、T は租税である。
(設問 1 ) 乗数に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。
- a 均衡予算乗数は、1 c 1 – である。
- b 政府支出乗数は、 1 c 1 – である。
- c 租税乗数は、1 c 1 – である。
- d 投資乗数は、1 c 1 – である。
(解答群)
- ア aとb
- イ aとc
- ウ bとc
- エ bとd
- オ cとd
[出典:https://www.j-smeca.jp/contents/010_c_/shikenmondai.html]
(解説)
この問題は、均衡予算乗数の定理についての出題です。
a 間違い
均衡予算乗数の定理は、政府支出乗数+租税乗数=1です。
b 正しい
問題文の通りです。
c 間違い
租税乗数は、-c/1-cです。
d 正しい
問題文の通りです。
これにより、正解はエになります。
この問題で必要になるのは、計算ではなく公式や定理の理解です。
計算に苦手意識のある方でも、均衡予算乗数の定理を覚えておくことで問題なく対応できます。
検証2.経済学・経済政策科目の過去問
問)ある遊園地では、入場料とアトラクション乗車料金の2部料金制をとっている。太郎さんがこの遊園地のアトラクションに乗る回数は1 回当たりの料金に依存するので、下図のような需要曲線Dが描けるとする。また、この遊園地がアトラクション乗車1回で負担する限界費用は200円であるとする。下図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
(設問)a 点Aにおいて太郎さんが支払う費用は1,200円である。
b 点Aよりも点Bの方が、太郎さんの消費者余剰は大きい。
c 入場料700円を支払った後に、点Aにおいて太郎さんはこのアトラクションに6回乗る。
(解答群)
ア a:正 b:正 c:正
イ a:正 b:正 c:誤
ウ a:誤 b:正 c:正
エ a:誤 b:正 c:誤
オ b:誤 b:誤 c:誤
[出典:https://www.j-smeca.jp/contents/010_c_/shikenmondai.html]
(解説)
経済・経済政策科目において難問とされています。
a 間違い
太郎さんが支払う費用は400×6=2400。
b 正しい
消費者余剰は、三角形の上限の700円と料金と点Aか点Bの面積になるため、点Aより点Bの方が消費者余剰は大きくなります。
c 正しい
入場料はサンクコストであり乗車回数には関係がありません。点Aにおいての乗車回数は6回です。
これにより、正解はウです。
消費者余剰分析に関する問題です。
消費者余剰に関しての知識があれば、数学の知識は四則演算程度のレベルで対応できます。
グラフに惑わされず、消費者のお得感を数値化した消費者余剰について、しっかり学びましょう。
検証3.財務・会計科目の過去問
問)以下の貸借対照表と損益計算書について、下記の設問に答えよ。
(設問 1 )固定長期適合率として、最も適切なものはどれか。
ア 60 %
イ 110 %
ウ 150 %
エ 167 %
(設問 2 ) インタレスト・カバレッジ・レシオとして、最も適切なものはどれか。
ア 4倍
イ 11倍
ウ 12倍
エ 14 倍
[出典:https://www.j-smeca.jp/contents/010_c_/shikenmondai.html]
(解説)設問1
固定長期適合率の計算式は次の通りです。
固定資産÷(固定負債+純資産)×100(%)
これによって、
=110,000÷(34,000+66,000)×100=110%となり
正解は、イです。
(解説)設問2
インタレスト・カバレッジ・レシオの問題は、次の計算式で解答できます。
=事業利益÷金融費用=(営業利益 + 受取利息・配当金) ÷ (支払利息 + 社債利息)
=(10,000+4,000)÷1,000=14倍
これにより正解はエです。
賃借対照表と損益計算書に関しては、多少計算が生じる部分もありますが、それよりも簿記に関しての知識が必要です。
簿記2級レベルの知識があると受験に有利になります。
数学知識が必要な科目の対策
この項目では、特に数学知識が必要な経済学・経済政策、財務・会計、運営管理の1次試験科目や2次試験における財務・会計テーマの対策について紹介します。
経済学・経済政策科目の対策
各経済の基本理論を理解し、数式を表や図で理解することに慣れる必要あります。
経済活動を理論的に説明する経済学では、デフレやインフレ、物価指数などの経済動向を数式や表、図などで表します。
そのため、数式を丸暗記するだけでは応用が効きません。
問題に解答するには、数式を表や図で理解する知識が必要です。
その知識の応用により、それぞれの経済現象をモデル化できるようになれば、問題を容易に理解できるでしょう。
財務・会計政策科目の対策
財務・会計政策では、ファイナンス(財務)とアカウンティング(会計)に関しての知識と正しい計算能力が必要です。
財務会計科目の問題では、会社経営上の資金に関する内容や計算問題が出題される可能性が高いためです。
アカウンティングでは、賃借対照表や損益計算書など、簿記に関する問題が出題されます。
財務諸表の役割や構造、主要な勘定科目などについてしっかり学び、棚卸資産や経過勘定などの計算はできるようにしておきます。
ファイナンスは資金調達と投資がメインテーマで、比較的理解しやすい分野です。
資本コストの概念を理解し企業価値や株価指標、デリバティブになどについて、基本的な計算ができるようにしましょう。
運営管理科目の対策
運営管理科目は幅広いテーマから出題されるため、過去の出題傾向をもとに勉強する範囲を絞りましょう。
出題されやすいテーマとしては、生産形態と生産方式や資材・在庫管理や品質管理、IEなどが挙げられます。
中でも、受注・見込生産、個別・ロット・連続生産、ライン生産、セル生産などについて理解は必須です。
難しい計算問題はないため、基本的な生産形態や方式、用語、特長を理解することで問題に対応できるでしょう。
事例Ⅳ(財務・会計テーマ)の対策
賃借対照表や損益計算表をもとに、分析する能力を身につけておきます。
事例Ⅳでは、財務諸表の計算・分析や経営課題の発見、改善提案などの計算問題や論述問題が出題されるからです。
過去の傾向によると、経営分析や設備投資の経済性計算、損益分岐点分析、キャッシュフロー計算、企業価値などのテーマから問題が頻出しています。
計算の正確性も求められるため、過去問を繰り返し解いて慣れておきましょう。
まとめ
この記事では、中小企業診断士の数学知識の必要性について紹介してきました。
中小企業診断士に、数学の難しい方程式や図形、微積分などに関する深い知識は必要ありません。
ただし、数式を図や表で理解する知識と正しい計算能力は必要です。
特に、1次試験の経済学・経済政策や財務・会計、運用管理科目、2次試験の事例Ⅳ(財務・会計テーマ)では、数式や表、図を用いた問題が出題されます。
各分野においての必要な知識を出題傾向から絞り、効率的に勉強しましょう。