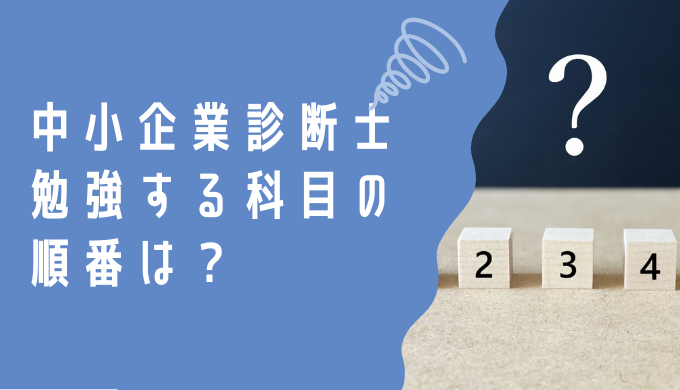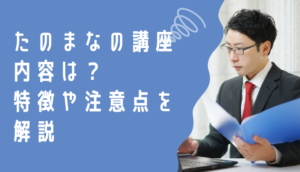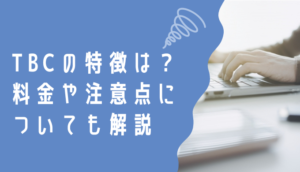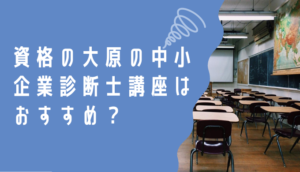「中小企業診断士は独学でも合格できるの?」
「独学で勉強する場合、効率的な科目の順番は?」
「とにかく効率的な勉強法が知りたい」
このような悩みをお持ちではないでしょうか。
中小企業診断士は、取得することで収入面のアップやキャリアアップなど多くのメリットが得られる人気資格です。
しかしながら、中小企業診断士は試験科目がとても多く、出題範囲がとても広い高難度の資格であり、誰でも簡単に合格できる訳ではありません。
また、受験する方の多くが社会人ということもあり、時間確保の難しく勉強が進まないという点から途中で挫折してしまう方もいます。
この記事では、独学で中小企業診断士合格を目指す中でそのような悩みを持つ方に向け、以下の内容で解説します。
- 中小企業診断士は独学でも合格できる?
- 中小企業診断士の勉強する科目の順番
- 独学で勉強する場合の順番以外のコツ4選
この記事を読めば、限られた時間の中でも効率的に勉強ができるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。
中小企業診断士は独学でも合格できる?
結論からいいますと、中小企業診断士は独学でも合格は可能です。
しかし決して簡単ではなく、非常に難しいということは理解しておく必要があります。
以下は中小企業診断士試験における近年の合格率です。
| 年度 | 一次試験合格率 | 二次試験合格率 | 試験合格率(一次+二次) |
|---|---|---|---|
| 平成29年度 | 21.7% | 19.4% | 4.2% |
| 平成30年度 | 23.5% | 18.8% | 4.4% |
| 令和元年度 | 30.2% | 18.3% | 5.5% |
| 令和2年度 | 42.5% | 18.4 | 7.8% |
| 令和3年度 | 36.4% | – | – |
過去5年間における、一次試験の合格率は約21~42%、二次試験の合格率は18~19%となっており、全体の合格率は約4~8%ほどとなっております。さらに過去の結果を含めると全体の合格率は概ね4%台となります。
上記結果の中には、予備校や通信講座を利用している方も含まれるため、合格は非常に狭き門であることがわかります。
独学の場合、特に大きな障害となるのが二次試験です。
一次試験はマークシート式のため勉強もしやすいのですが、二次試験は記述式で決まった解答というものがほとんどありません。
そのため、個人では対策が取りにくく独学合格の難度を大きく引き上げています。
以上のように、そもそもの合格率が低く二次試験の対策も取りにくいことから、独学での合格は非常に困難といえるでしょう。
しかし最初にお伝えしたように、独学での合格は不可能ではありませんし、実際に独学で合格した方もいます。
ただし、限られた時間しか使えない中で合格するためには、効率的な勉強方法や長期的な勉強計画が必要不可欠です。
中小企業診断士を独学で合格を目指す場合は勉強の順番が重要
中小企業診断士の一次を効率的に勉強する上で、勉強する科目の順番は非常に重要になります。
以下が、中小企業診断士を独学で勉強する場合の、おすすめの勉強順です。
| 順番 | 科目 | 重要度(A>C) | 二次試験関連度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 企業経営論 | A | 高 |
| 2 | 財務・会計 | A | 高 |
| 3 | 運営管理 | A | 高 |
| 4 | 経済学・経済政策 | B | 低 |
| 5 | 経営法務 | B | 低 |
| 6 | 経営情報システム | C | 低 |
| 7 | 中小企業経営・政策 | C | 低 |
では、なぜこの順番がよいのでしょうか。
詳しく解説します。
理解が重要な科目を優先
中小企業診断士試験の科目には理解することが重要な「理解度重視」科目があります。
具体的な科目でいうと「企業経営論」「財務・会計」「運営管理」「経済学・経済政策」の4科目が「理解度重視」科目にあたります。
「理解度重視」科目をしっかりと身につけるためには長い時間が必要です。
また「理解度重視」ということもあり、一度理解すれば忘れにくく、もし忘れてしまっても問題演習などですぐに思い出すこともできます。
以上の理由から「理解度重視」科目を優先的に勉強することで効率的な学習が可能です。
特に「企業経営論」「財務・会計」「運営管理」の3科目は、二次試験とも密接に関わる最重要科目です。
より確実に理解する必要があるため、最初期から勉強をはじめましょう。
暗記が重要な科目は後半
「理解度重視」とは反対に暗記が大きな割合を占める「暗記重視」科目があります。
具体的には「経営法務」「経営情報システム」「中小企業経営・政策」です。
暗記がメインのため、勉強後半でも対処がしやすい上に、あまり早い段階で勉強してしまうと試験前に内容を忘れてしまい、再度勉強が必要という手間が発生しかねません。
また「暗記重視科目」は二次試験と関連が低い科目も多いため、重要度も「理解度重視」科目よりは低いです。
以上の理由により「暗記重視」科目は後半に勉強するのが効率的です。
独学で最優先で勉強すべき3科目について解説
ここでは、最優先で勉強すべき3科目である「企業経営理論」「財務会計」「運営管理」の概要について科目別に解説します。
企業経営理論
企業経営理論は中小企業診断士の土台となる、最も重要な科目です。
土台となるだけでなく、二次試験との関わりも深く確実に理解しなければならない科目といえます。
企業経営理論は、大きく分けて「経営戦略論」「組織論」「マーケティング論」の3つにわかれており、企業の現状分析や問題解決について勉強します。
ビジネスマンにとっては馴染み深いリーダーシップやマネジメントといったテーマも多く、入りやすい科目でもあり、モチベーションの維持もしやすいでしょう。
財務・会計
財務・会計は簿記の知識が必要で、事前知識がない方にとっては最も時間が必要な科目です。
また、二次試験との関連するため重要な科目といえるでしょう。
財務・会計は財務諸表の読み方など経営分析に関わる内容で、計算問題が多い科目でもあります。
また、試験当日は電卓を使うことができません。
そのため、簿記の基礎を勉強したあとは、問題演習を何度も繰り返して正確性とスピードを鍛えていきましょう。
運営管理
運営管理は、重要科目の中では比較的得点しやすい科目です。
しかし上記の2科目同様、二次試験とも関係する重要科目のため、しっかりと勉強が必要になります。
内容は「生産管理」「店舗・販売管理」の2つの分野から構成されており、知識があれば解答できる問題と、知識を使って計算する問題が出題されます。
また、特徴として「企業経営理論」「財務・会計」よりも暗記の割合が多い科目です。
そのため、場合によってはスケジュールの後半に勉強するのもひとつの方法になります。
独学で中盤に勉強すべき2科目について解説
次に中盤に勉強すべき「経済額・経営政策」「経営法務」の概要について科目別に解説します。
経済学・経済政策
経済学・経済政策は、人によっては最大の壁として立ちはだかる科目になります。
この科目では図やグラフの読解にくわえ、計算問題が多数出題されます。
特に、図・グラフの読解は慣れない内は非常に難しく感じるでしょう。
高得点を狙うには、主だった理論にくわえ、数学的な勉強が必要になります。
出題率の高い理論をしっかりと理解し、問題演習や過去問を繰り返して理解を深めていきましょう。
また、新聞やWebなどで主要なニュースをチェックするのも重要です。
経営法務
経営法務は、年度によって難易度のバラつきが出やすい科目です。
経営に関わる法律について学ぶ科目であり、その出題範囲は非常に幅広く、完璧を目指すと多くの時間が必要になります。
出題傾向には偏りがあるため、出題が予想される問題は確実に解答できるように準備した上で、難易度が高すぎる問題に関しては切り捨てる覚悟も持っておきましょう。
経営法務にスケジュールを取られすぎて、ほかの科目に使える時間が少なくならないようにバランス配分が重要です。
独学で後半に勉強すべき2科目について解説
最後に、後半に勉強すべき「経営情報システム」「中小企業経営・政策」の概要について解説します。
経営情報システム
経営情報システムは情報技術に関わる専門用語が多く出てくるため、ITに詳しくない場合は少し苦労する科目です。
逆に、必要なIT知識そのものはあまり高度ではなく、ITパストートなどを取得している場合は対策は容易になります。
暗記重視の科目のため、テキストや問題集を繰り返して内容を定着させましょう。
また関連度は低いですが、二次試験においても基礎的なIT知識は問われる場合があるので注意してください。
中小企業経営・政策
中小企業経営・政策は問題のほぼすべてが、毎年4月に発行される「中小企業白書」から出題されます。
「中小企業白書」だけを勉強すればよく、覚える内容自体は多いですが対策を取りやすい科目でもあります。
一方、過去問から出題されることはないため、過去問による対策は取ることができません。
科目全体で見れば最も難易度の低い科目ともいえるので、勉強できる期間が短い点だけには注意して、確実に合格を狙っていきましょう。
中小企業診断士を独学で勉強するその他のコツ4選
ここでは、独学で効率的に勉強するコツを4つ、以下の内容で解説します。
- 複数の科目を並行して学習する
- 二次試験を踏まえつつ一次試験の勉強をする
- なるべく早く過去問・問題集に取り掛かる
- 毎日継続して勉強する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.複数の科目を並行して勉強する
中小企業診断士の各科目の出題範囲はとても広いです。
そのため、1科目だけに集中して勉強を進めていては飽きてしまいかえって効率が落ちてしまいます。
また、中小企業診断士に合格するためには約1,000時間の勉強が必要といわれており、基本的には長期的なスケジュールになります。
そのため一度勉強した内容でも、定期的に復習をしておかないと忘れてしまう恐れがあります。
「勉強時間の8割はメイン科目の勉強、2割は復習」や「勉強中の科目が行き詰まった時にほかの科目の勉強」といった具合に、複数の科目を並行して勉強することで、勉強にメリハリがつくことにくわえ、勉強した内容を維持することが可能です。
2.二次試験を踏まえつつ一次試験の勉強をする
中小企業診断士試験に慣れている方や時間に余裕がある場合は、二次試験を踏まえつつ一次試験の勉強をしましょう。
しかし、これは一次試験の勉強中に二次試験対策をしろという訳ではありません。
中小企業診断士の二次試験においては、当然ながら一次試験を合格した前提で出題されます。
そのため、二次試験の問題を的確に読み解くためには、一次試験で身につけた知識が必要不可欠です。
特に、前述した最重要科目である「企業経営理論」「財務・会計」「運営管理」の一定以上の理解は必須といえるでしょう。
そのため、一次試験の各科目の理解を深めることが二次試験の勉強にもつながります。
その点を意識して、特に関連の深い科目についてはしっかりと理解を深めるよう勉強しましょう。
二次試験の対策自体は、一次試験合格後でも問題ありません。
3.なるべく早く過去問・問題集に取り掛かる
中小企業診断士を含め、すべての試験合格において、過去問の活用は必要不可欠です。
過去問を実施することで自身の勉強になるのはもちろんのこと、実際の試験のレベルや問題の出題傾向など、合格には欠かせない多くの情報を手に入れることができます。
このように重要な役割を持つ過去問ですが、取り組み始めるタイミングは一通り勉強を終えた時である方がほとんどです。
しかし、より効率的に勉強を進めるためには、普段の勉強から積極的に活用していくことをおすすめします。
早い段階から過去問に取り組むことで、試験の傾向や頻出問題が把握できる上に、必要なレベルと自身の差が明確になります。早い段階で自身の課題が明確になれば、今後のスケジュール調整もしやすく効率的な勉強が可能です。
ただし「中小企業経営・政策」の科目だけは注意が必要です。
概要でも説明したように、この科目は過去問からは出題されません。
そのため「中小企業経営・政策」の過去問をする場合は、参考程度に取り組みましょう。
4.毎日継続して勉強する
中小企業診断士試験は長期的な勉強が必要です。
長期的な勉強において「モチベーションの維持」や「勉強の習慣化」はとても重要です。
モチベーションを維持できるかが、合格を左右するといっても過言ではありません。
そのため、どれだけモチベーションが上がらなくとも少しでもよいので勉強に関わる行動をしましょう。
内容自体は「1日5分」「動画を1本」「本・パソコンを開くだけ」でもかまいません。
少ない行動でも「勉強を毎日続けている」という事実が自信や習慣化につながるでしょう。
中小企業診断士に独学で合格するための学習スケジュール
中小企業診断士に合格するためのスケジュールは「いつ勉強を開始したか」によって変わります。
6~11月ごろに勉強を開始した場合、8月の試験まで1年近くの時間を勉強に使うことが可能です。
1年あれば合格を狙うことも十分可能なので、1発合格を狙って勉強を進めましょう。
一方、12~5月ごろに勉強をはじめた場合、半年ほどで試験に挑むことになります。
この場合、ストレートで合格するのはかなりの難易度です。
そのため、最終的な合格は翌年度として1年目は科目合格を狙っていきましょう。
1年目に狙う科目としては「経済学・経済政策」「中小企業経営・政策」などがおすすめです。
この2科目は二次試験との関連も低く、改めて勉強する必要も少ないので、翌年度の勉強において一次試験・二次試験の対策を同時にしやすくなります。
まとめ
中小企業診断士試験を独学で合格する場合における、科目の順番や勉強のコツ、スケジュールについて解説しました。
中小企業診断士を独学で合格することは決して簡単ではありません。
しかし効率的な勉強方法の実施や、しっかりとした勉強計画を立てることができれば決して不可能ではありません。
中小企業診断士試験において、効率的に勉強するためには科目の勉強する順番がとても重要になります。
この記事で紹介した、勉強の順番やコツなどを参考にして最短で合格を勝ち取りましょう。